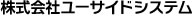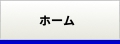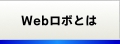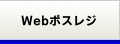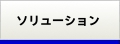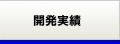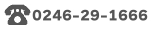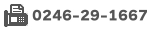ホーム > 今、ソフト産業が問われているもの

日本のソフト産業は2年前までの深刻な人手不足という状況から一転、深刻な仕事不足に陥っています。
その背景にはグローバルな情報化時代ながら、そのインフラを支えるべきソフト産業の深刻な実態を反映しているものと思います。
本来なら不況と言えども、クラウドコンピューテング、仮想化技術、iPadに代表される情報端末の進化及び低価格化により新たな可能性が開け、 新たなビジネスチャレンジの動きが起こらなくてはならないはずです。 しかしながら東京より聞こえてくる話は、新規案件のなさと深刻な仕事不足です。ここにソフト産業の深刻な体質があります。
日本のソフト産業はもともと戦後、NTTを頂点とした電話産業が母体になり、 NTTの電話製造の下請であった富士通、NECを筆頭としてそうした製造会社がコンピュータ―製造を担い、 そのコンピューター販売の必要性より、ソフトの開発をするようになってまいりました。 したがって、ソフト開発における人事管理手法は製造業におけるスタンダードタイム手法がそのまま時間単価による評価基準になり、 人工制度として取り入れられるとともに、製造業の下請け制度がそのまま引き継がれることになったものと思います。 ここに、中国、インドなどの優秀なベンチャー的人材がソフト開発業をはじめることになったこととは歴史的背景を異にしています。
一方、ソフト産業はバブル崩壊の影響で多少の浮沈はあったものの、不況対策としてITが国家的戦略として位置づけられ、 不況脱出以後の好況により一層の重層的な下請け化と派遣制度が進みました。 しかしながらその間日本のコンピューターメーカーは、マイクロソフトによるOSの世界制覇を受け、独自なオフコン製造を失うとともにOSの開発を失ない、 Linux、Java等のオープンな環境での技術習得と開発の意欲まで失うことになりました。 しかしながら好況の影響で、受身でも仕事が舞い込み、金勘定が重要な仕事になり、一層の下請け利用により技術の空洞化が進みました。 その下請け化はオフショアを結果することになり、大手メーカーの技術的空洞化にとどまらず、国内の空洞化を結果しました。 また、人工制度はいかに安い人材をいかに高く売るかという方向に向かい、派遣化と人材の劣化と生産性の低下及びソフト産業の社会的評価の低下を招き、 国際競争力を失うことになりました。
また、下請け制度、派遣制度はソフト産業経営者よりリスクにチャレンジするマインドを奪うことになり、みずからその技術と社会のニーズを汲み取り、 新たなビジネスをクリエイトする気概を失わせることになりました。
日本のソフト産業の会社名にソリューションという名前を冠し、またソリューションを標榜する会社がいかに多いことか、 自らの問題解決能力を失っているものが他者の問題解決を標榜している皮肉、今自らそのことを認識することの必要性を感じます。
インターネットの進化により、ますますグローバルな競争を強いられることになりますが、これまでの日本の大手ベンダーの戦略としてきた、 企業規模拡大という手法が果たしてユーザーの信頼獲得手段として有利な戦略であり続けるでしょうか。
今回のリーマンショック以降の不景気により、様々な動きが出てきています。 それまで大手ベンダーに依存することが中小ソフト企業にとって最も確実な戦略でしたが、 ここにきて大手ベンダーよりの仕事を待っていては日干しになってしまうという危機感であり、自ら顧客を獲得する動きです。
また、ユーザーのコスト意識の高まりで、ブランドの対価として高額な費用を支払う余裕が特に地方においては困難になってきています。
本来コンピューターメーカーはハードの開発、OSの開発により技術的なリーダーとしての役割をにない、 全国デーラーに対して指導力を発揮するとともに中央の仕事を地方に配分する機能を有し、それなりの利鞘を得る根拠としてきました。
しかしながら、Web開発においては開発ツール、開発手法についてなんら指導力を発揮せず、また人件費の安さを理由にオフショア開発を進め、 仕事のデリバリー機能を放棄して上でのべた様にソフト産業の国内空洞化を結果させてきています。
巨大化だけでは恐竜が絶滅したように、ユーザー及び社会にメリットのある存在根拠を持った戦略でないかぎり、時代の変化に対応できず衰退することは明白です。
蛍は暗くなくては目立たないものですが、この不況においてはじめて弊社の「Webロボ」は関心を寄せていただいています。
今問われていることは企業の大小ではなく、ユーザーが求める自立的なノウハウを有しているかどうかではないでしょうか。